有料職業紹介事業許可
| ■ 職業紹介事業の概要 |
職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において、①求人及び②求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における③雇用関係の成立を④あっ旋することをいいます。
① 求人 … 報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること。
② 求職 … 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすること。
③ 雇用関係 … 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係のこと。
④ あっ旋 … 求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすること。
職業紹介は、人材派遣と並ぶ人材ビジネスで、求人企業が求める人材をその企業に紹介・斡旋することを業として行う事業です。
この職業紹介事業は、従来、国営の公共職業安定所(ハローワーク)が独占し、民間業者については、職安機能を補完する形で部分的・例外的に認められていました。民間企業が行う職業紹介については、対象となる職種は、看護婦・家政婦紹介、配ぜん人紹介、マネキン紹介、経営科学者紹介、芸能人紹介など29職種に限定されていましたが、平成11年の規制緩和によって紹介職種や斡旋手数料などが原則自由化されました。
最近では、事務的職業や販売・営業的職業、技術的職業、管理的職業などのいわゆるホワイトカラーの職業紹介事業が注目を集めています。
| ■ 職業紹介事業の種類 |
民営職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。
1.有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介 事業をいいます。 有料職業紹介事業は、職業安定法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります)以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
2.無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
無料職業紹介事業は、
| 1. | 一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、 | |
| 2. | 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33 条の2の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、 | |
| 3. | 商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、 | |
| 4. | 地方公共団体が行う場合には法第33条の4の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、 無料職業紹介事業を行うことができます。 |
| ■ 許可取得までのスケジュール |
|
1ヶ月目
|
・ご依頼 ・当事務所にて事前打ち合わせ ・労働局との事前協議 ・許可申請 ・労働局書類審査 |
| 2ヶ月目 | ・労働局より事業所調査の日程連絡 ・事業所調査の実施(事業所に労働局の調査官が来ます) ・労働局から厚生労働省へ進達 ・厚生労働省書類審査 |
| 3ヶ月目 | ・労働政策審議会 ・厚生労働省から労働局へ許可予定事業所の連絡 |
| 4ヶ月目 | ・1日頃に許可日 ・許可書の交付 |
※ 許可申請を行なってから、許可取得まで3ヶ月くらいかかります。お急ぎの場合はお早めにご相談ください
| ■ 有料職業紹介事業の許可要件 |
有料職業紹介事業を行う場合、事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に許可申請しなければなりません。
許可を受けないで、有料職業紹介事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(職業安定法 第64条第1項)。
申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。
■ 欠格要件
| 1. | 禁錮以上の刑に処せられ、又は労働に関する法律等の規定を犯したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者 |
| 2. | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| 3. | 職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの |
| 4. | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの |
| 5. | 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの |
許可申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。
■ 許可要件
| 1. | 有料職業紹介事業を行なおうとする事業主が財産的基礎を有すること。 財産的基礎とは、直前の財務諸表により次の算式で判断します。 基準資産 = 資産の総額 - (営業権+繰延資産) - 負債の総額 以上基準財産が、以下のいずれにもあてはまること。 ・基準資産 ≧ 500万円 × 事業所数 ・現金・預金の額 ≧ 150万円 × (事業所数 - 1)×60万円 |
| 2. | 個人情報を適正に管理し、求人者・求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられること。 |
| 3. | 職業紹介責任者を設置すること。 職業紹介責任者は次のいずれかにも該当すること。 ・成年に達した後、3年以上の職業経験を有する者 ・労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関する経験を有する者 社団法人・全国民営職業紹介事業協会(外部サイト)にて申込が必要です。 〒113-0033 東京都文京区本郷1-34-3 本郷木口ビル5F TEL 03-3818-7011 FAX 03-3818-7015 |
| 4. | 事業所の面積がおおむね20㎡以上あること。 |
| ■ 有料職業紹介事業許可申請に必要な書類 |
有料職業紹介事業を行おうとする場合には、次に掲げる書類を申請者の所在地(申請者が法人の場合には、その主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
この場合、許可申請書には、手数料として〔5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数-1 〕分の収入印紙を添付する必要がありますが、都道府県労働局の指示に従ってください
なお、収入印紙が消印された後は手数料は返還されません。
1.有料職業紹介事業許可申請書(様式第1 号)3 部(正本1 部、写し2 部)
2.有料職業紹介事業計画書(様式第2 号)3 部(正本1 部、写し2 部)
3.届出制手数料届出書(様式第3 号)3 部(正本1 部、写し2 部)
※3については、上限制手数料による場合には提出は不要です。
4.添付書類2 部(正本1 部、写し1 部)
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2 カ月前までに行う必要があります。
| 必要とされる添付書類 | 法人の場合 | 個人の場合 | ||||
| 定款又は寄附行為 | ○ | |||||
| 法人の登記簿謄本 | ○ | |||||
| 住民票の写し | ○ | ○ | ||||
| 履歴書 | ○ | ○ | ||||
| 代表者役員の法定代理人の住民票の写し及び履歴書 | ○ | ○ | ||||
| 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 | ○ | ○ | ||||
| 預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類 | △ | △ | ||||
| 所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書 | △ | △ | ||||
| 最近の事業年度における納税申告書の写し | ○ | ○ | ||||
| 最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書 | ○ | ○ | ||||
| 個人情報適正管理規程 | ○ | ○ | ||||
| 業務の運営に関する規程 | ○ | ○ | ||||
| 建物の登記簿謄本 (申請者の所有に係る場合) |
○ | ○ | ||||
| 建物の賃貸借又は使用貸借契約書 (他人の所有に係る場合) |
○ | ○ | ||||
| 手数料表 (届出制手数料の届出をする場合) |
○ | ○ | ||||
| 相手先国に関する書類 (国外にわたる職業紹介を行う場合)
|
○ | ○ | ||||
| 取次機関に関する書類 (国外にわたる職業紹介を行う場合であって、取次機関を利用するときに限る。)
|
○ | ○ |
| ■ 許可取得後の手続について |
許可有効期間について
有料職業紹介事業の許可の有効期間は新規については3年、更新については5年となります。
無料職業紹介事業の許可の有効期間は新規・更新とも5年となります。
引き続いて職業紹介事業を行う場合には、許可の有効期限が満了する日の30日前までに許可更新申請を行う必要があります。
■ 変更届出等について
| 事 項 | 手 続 | ||
次の変更
|
変更届出 (事後10日以内、8.9.は事後30日以内) |
||
| 事業所の廃止事 | 業廃止届出(事後10日以内) | ||
| 取扱職種範囲の変更 | |||
| 届出制手数料の変更 | |||
| 事業所の追加 | |||
| 職業紹介事業報告 | 毎年4月30日までに | ||
| 個人事業主の死亡 | 死亡届(事後10日以内) |
| ■ 有料職業紹介事業で取り扱うことができない職業 |
有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料職業紹介事業においてその職業のあっ旋を行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして命令で定める職業以外の職業です。
なお、この命令で定める職業は現在定められていません。
港湾運送業務
港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として命令で定める業務。
建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務。
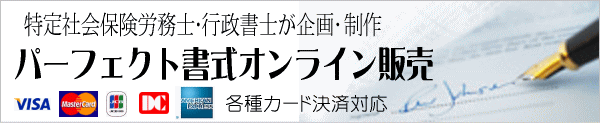
Page Top
【 関連サイト 】